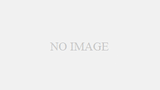人の基本は、自然と共に生きること
人間は自然の一部であり、自然と共に生きること、太陽の昇降や季節に合わせ活動し、その時季に取れる食材をたべること。 私たちの体は、生きている土地の環境に合うようになっています、その土地で育った季節の産物には 生きる上で必要な作用や栄養が備わっており、それを摂ることで健やかな体つくりにつながるのです。 遠い昔からお米を食べ、季節の野菜などを主菜にしてきた日本人にとって、最近のいきすぎた食の欧米化は身体に合わなくなってきています。
菜食薬膳に注目する理由
不調の改善や健康維持ににつながる、 暑いときには元気が出る食べ物を撮ろうとしたり、寒い日は身体が冷えないように注意します。 こうした、気候や環境に応じた考えや対応が身体の健康維持につながっています。 季節による体の変化に対応しやすい、 季節や体質に合わせて、食材の旬や性質など利用して食養生します。 菜食は日本人の古来からの料理 菜食料理は現代人の野菜不足の解消に役立つ
薬膳とは健康になるための料理
「薬(医)食同源」、食養生といった思想があり、食材のもつ力で、免疫力を向上させて、病気を予防したり、体の不調を改善させたりすることができると考えられてきました。
参考資料 日本創芸学院 菜食薬膳講座より抜粋
その他の食に関する建康方法
昭和48年(1973年)~昭和55年(1980年)ごろに”古代食と言う提案”があり、新聞やテレビでも取り上げられました。 遥か昔の古代人(縄文から弥生時代の人々)に肥満の人は一人もいない。 草食動物と肉食動物の腸の長さを比べてみると、草食動物の腸の方がずっと長いものですが、東洋民族は西洋民族に比べ、約2倍もの腸の長さを持っていて、日本人も例外ではないそうです、 元々日本人は農耕民族で、玄米、野菜、野草、海藻を食べ、動物性タンパク質と言っても小動物、貝類、小魚であった。 これは、古代の貝塚などでもよく見られる事象です。 古代食は菜食中心の食事です。(これは、菜食薬膳に通じるものがあります。) 古代食の調理法の原則 穀類を主食にする。 豆類を常に添える。 副食は菜食とする。 砂糖や調味料類は使わない。 やむおえず使う場合は、天然醸造の味噌、荒塩、純粋のごま油 にする。
やっと手頃なお米が販売されるようになりましたが、多く購入されてお家で保管される時は必ず、保存袋を使用しましょう、梅雨入りすれば米の虫が発生するかもしれません。